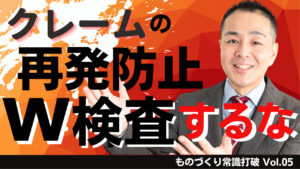【間違いだらけの】品質管理|クレームを激減させるたった1つの【秘訣】

🔍 クレームの原因の本質
多くのクレームは“人のミス”による再発である。
再発防止の根底には「人がミスをしないようにする」という前提があるが、それ自体が間違っている。
🤯 前提を変えるだけで激減
“人はミスをするもの”という前提に切り替えることで、クレームは激減できる。
🧠 フールプルーフの考え方
人がミスをしても問題が起こらないように設計する=フールプルーフ。
例:電子レンジの扉が閉まらないとスタートしない。
✉️ 郵便物の工夫例
透明封筒で宛名と中身が一致していることを確認できる。
→ 人のチェックミスを構造で防止。
🚗 製造現場での工夫
左右パーツの間違い防止のために梱包方法に工夫を加える。
💧 時代遅れの常識の危険性
かつての「運動中は水を飲むな」という常識のように、
今の品質管理の常識も見直すべき。
🔁 繰り返しの対策に限界あり
ダブルチェックや注意喚起だけでは限界。
根本的に仕組みを変える必要がある。
🔧 必要なのは“抜本的な見直し”
今こそ従来のやり方から脱却し、新しい視点から品質管理を再構築すべき時。
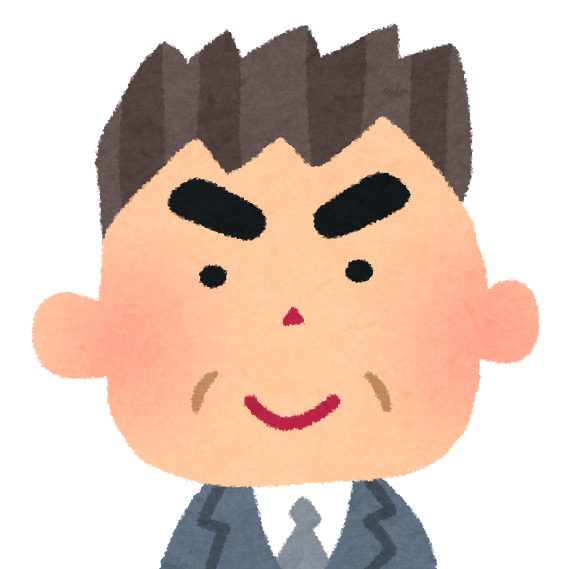 経営者
経営者クレームを激減ですか・・・ズバッと来ましたね!そんなことできるのですか?
 カスヤ
カスヤはい、もちろんできますよ。
 カスヤ
カスヤクレームを無くしたいという思いは、経営者・管理者であれば誰でも持っていますよね。
 カスヤ
カスヤそこで今回は、クレームを激減させる方法をお伝えします。
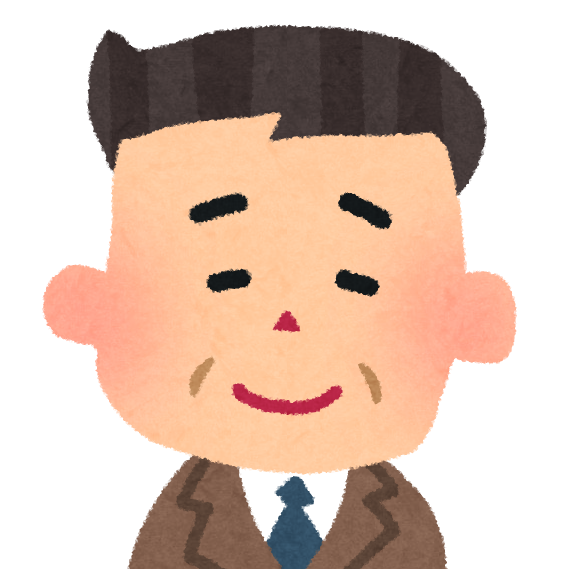 経営者
経営者私の所では、クレームが発生すると、原因と対策を考え、再発防止策を打っています。それでも、全然クレームが減らないんです。
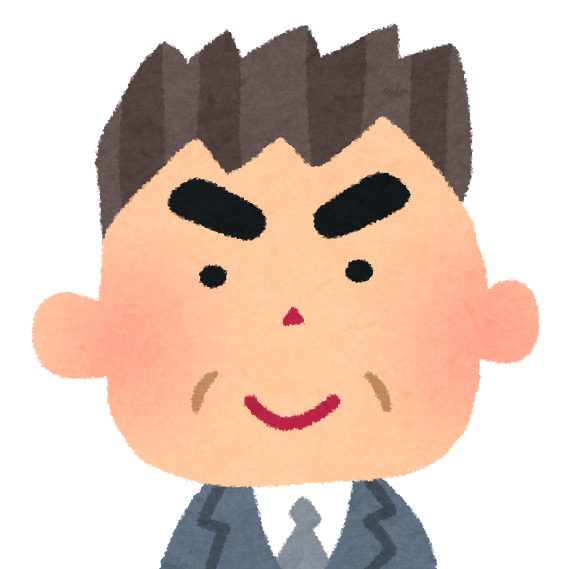 経営者
経営者そうだよね、原因究明、対策立案はやれていると思っているんだよ。これは当たり前のことだろ?
 カスヤ
カスヤそれは素晴らしい取り組みです。その当たり前のことができていない工場が多いんですよ。
 カスヤ
カスヤでは、原因究明、対策立案ができているということですので、話を進めます。
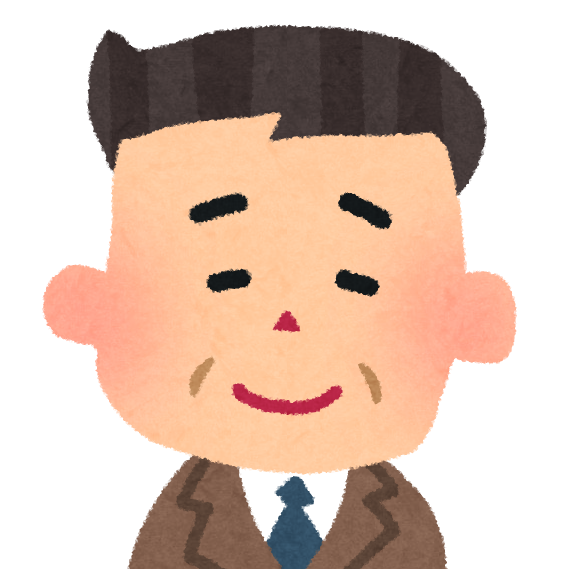 経営者
経営者原因究明、対策立案のやり方ということではなさそうですね。
品質管理|クレームを激減させるたった1つの【秘訣】
 カスヤ
カスヤクレームの多くは再発であり、そして人のミスに起因することが大多数です。
 カスヤ
カスヤそしてクレームが起きると、原因と対策を考え、再発防止策を打ちますよね。
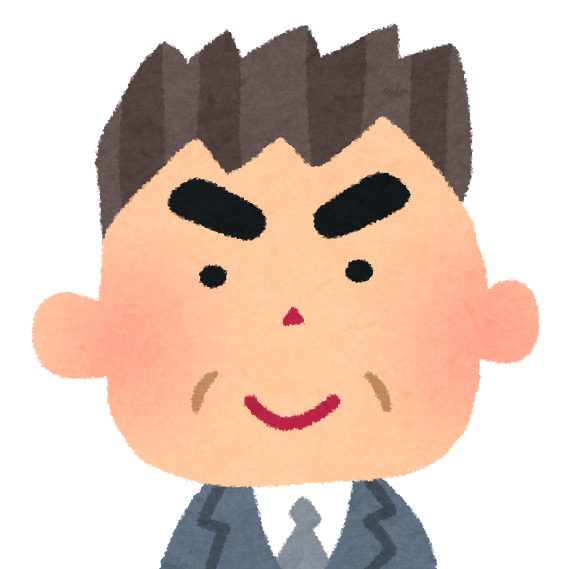 経営者
経営者おっしゃる通り。
 カスヤ
カスヤ実はその対策の根底にある『前提』が間違っているんです。
 カスヤ
カスヤその前提とは、『人がミスをしないようにするには、どうすればいいか』ということです。
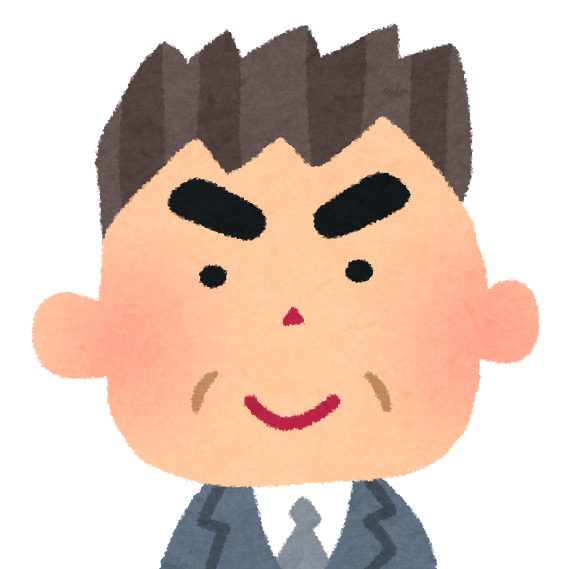 経営者
経営者人(作業者)がミスをしないようにするために対策をしているのではないですか?
 カスヤ
カスヤでは、どのような対策をしているんですか?
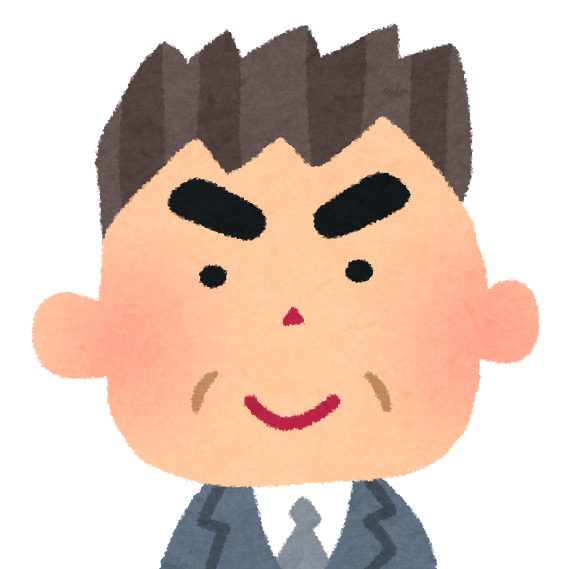 経営者
経営者原因のほとんどが、作業者の「思い込み」「勘違い」「チェック漏れ」・・・だから・・・
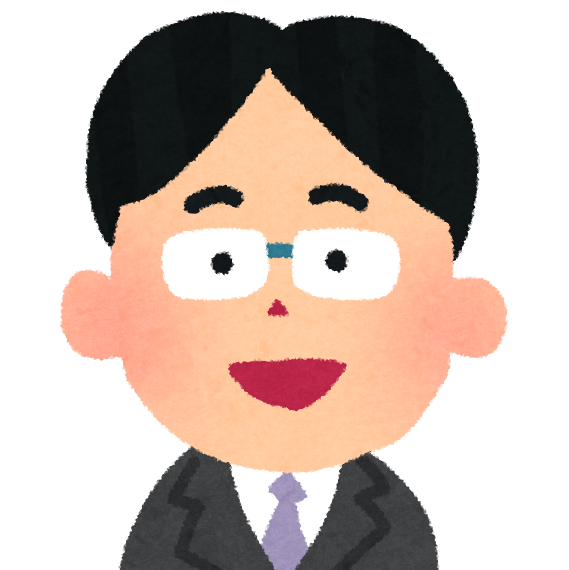 経営者
経営者「確認を徹底する」とか「ダブルチェックする」という対策です。
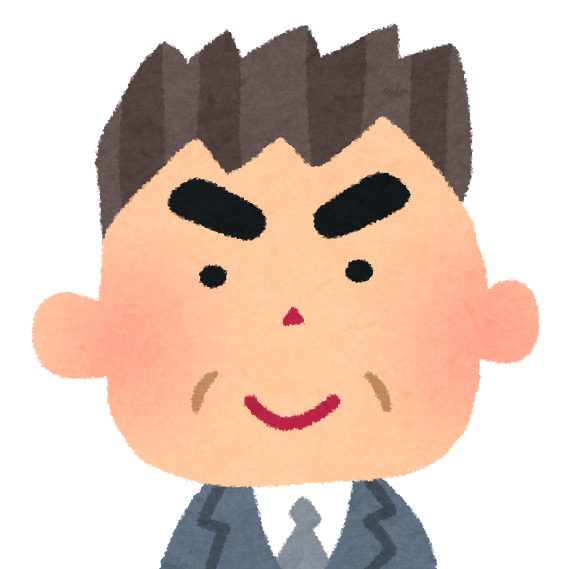 経営者
経営者そう、それだよ、それ!でもさ、それを徹底しているつもりなんだけど、クレームが減らないんだよな~
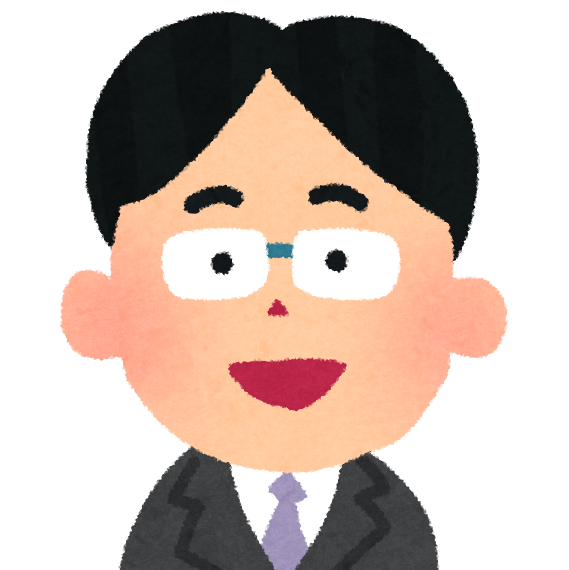 経営者
経営者確かに、徹底確認します!と勢いよく言いながら、クレームが出ますもんね~
 カスヤ
カスヤははは、困ったもんですね。
 カスヤ
カスヤいいですか、重要なので、よく聞いてください。
 カスヤ
カスヤそれらの対策の根底にあるのは『人がミスをしないようにするには、どうすればいいか』という前提ですよね。
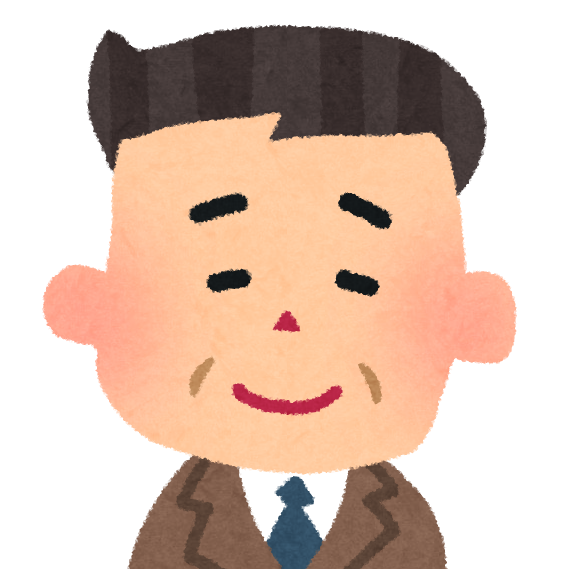 経営者
経営者はい、それは理解しました。
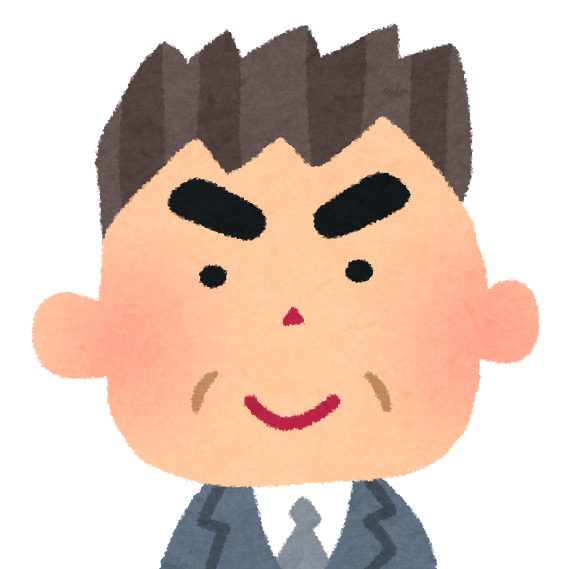 経営者
経営者まー、なんとなく・・・
 カスヤ
カスヤ実は、この前提を変えると、ガラッと変わるんです。
 カスヤ
カスヤそれは『人はミスをするものだから、どうすればいいか』です。
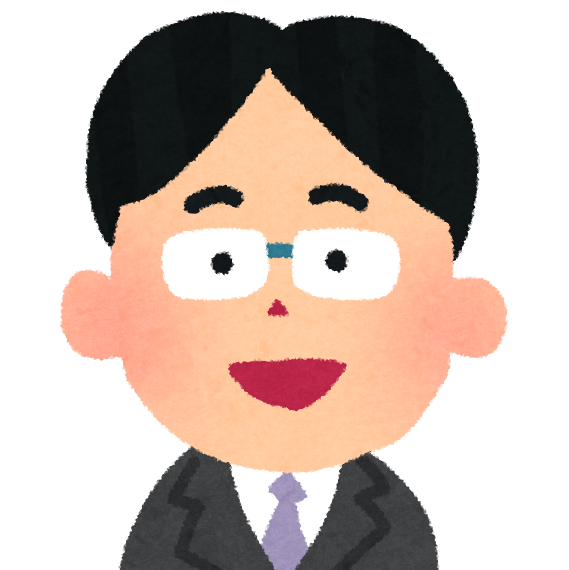 経営者
経営者なんとなく、見方が変わるかも・・・
 カスヤ
カスヤこのように、人がミスすることを受け入れてしまうんです。
 カスヤ
カスヤ人(作業者)を信用するな!ミスをすることを前提に対策を考えよということです。
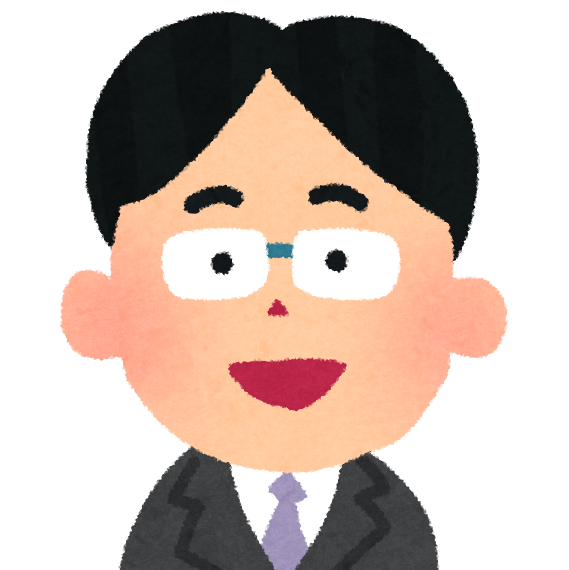 経営者
経営者言われてみれば、そうかもね!
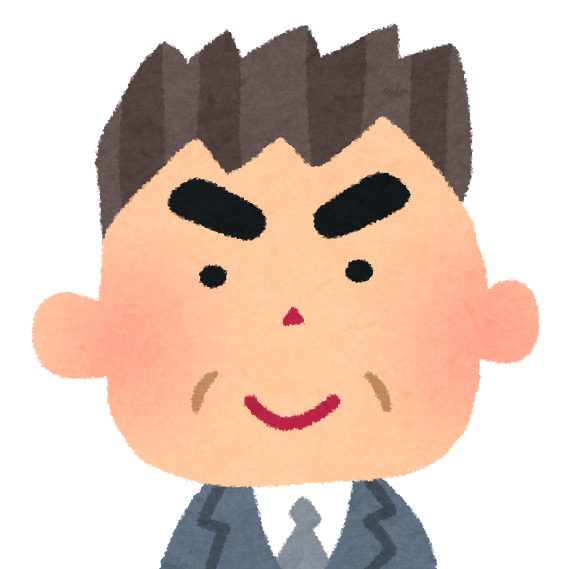 経営者
経営者なるほど、人がミスをしたくてもできないようにする・・・ということですか?
 カスヤ
カスヤその通りです。素晴らしいですね。前提を変えることで、発想転換ができたじゃないですか。
 カスヤ
カスヤこれを『フールプルーフ』というんです。
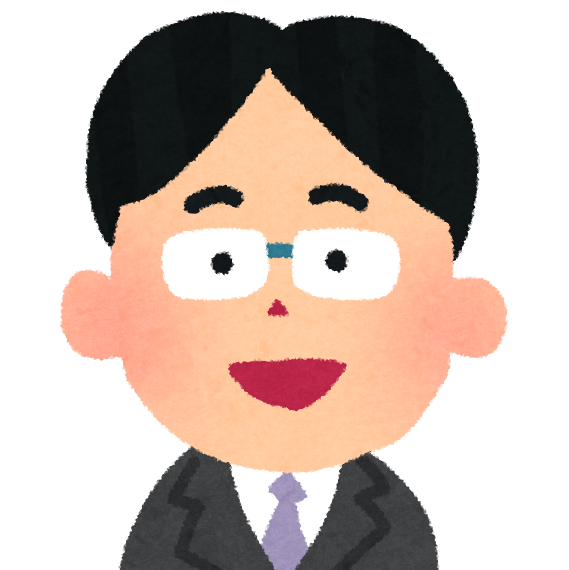 経営者
経営者何だか、美味しそう!
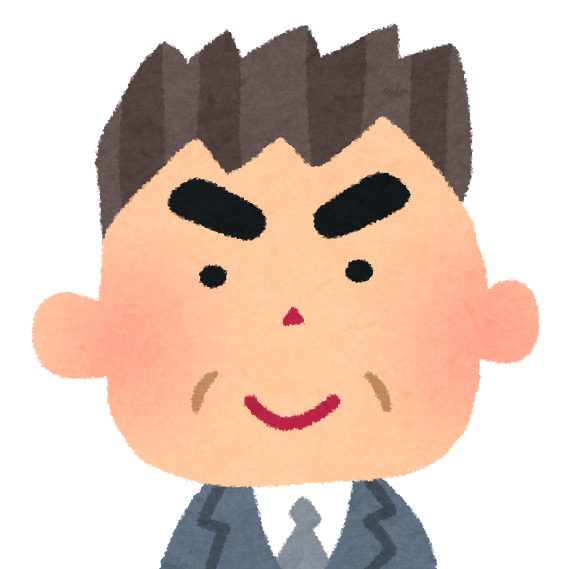 経営者
経営者食べ物じゃないよ。どこかで、聞いたことあるな!
 近江
近江1つの新しいアイデアが世界を変える!すなわちクレームを激減させる。
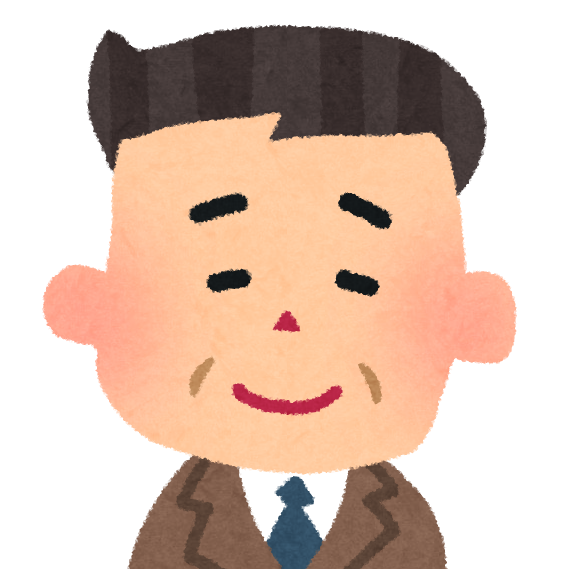 経営者
経営者なるほど、新しい挑戦をせよ!ということですね。
 カスヤ
カスヤフールプルーフをご存じの方もいますよね。
 カスヤ
カスヤ簡単に言うと、人がミスをしたくてもできないように設計するというものです。実はこれは私たちの身近に応用されているんです。
 カスヤ
カスヤでは、その具体的な内容について詳しく話をしていくので、動画を最後まで見ていってくださいね。